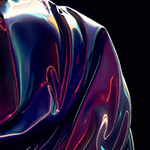@もりもり
そうですね。まずは製品版を購入していただくことをおすすめしますが、パースをオフにすることで求めている挙動になると思います。
kizakiaoiさんの投稿
-
RE: TransposeブラシをAlt+ドラッグで動かした際の挙動についてZBrushヘルプに投稿されました
-
RE: TransposeブラシをAlt+ドラッグで動かした際の挙動についてZBrushヘルプに投稿されました
すみません、いまいち文章を読んだ限り何を求めているのかがわからないのですが
①移動モードでトランスポーズアクションラインを配置後、ALT+ドラッグ使用しメッシュを移動させた場合と
②トランスポーズアクションライン中央の円を左ドラッグした時の動き
を比較したものです。https://gyazo.com/47438a39ad843dfe56007d47a7144f0f
そこで、もりもりさんが求めている内容として、"対象もマウスポインタと一緒に移動してくれることです。"とのことですが、どちらも同じく、対象 = 対象のメッシュとした場合、"マウスカーソルの動きに追従している"と思うのですが、具体的に現在どのような動作をしていて、どのような動作を求めているのでしょうか。
-
RE: ペンタブ操作に関する質問ZBrushヘルプに投稿されました
@ショカコーラ
ペンタブの種類の記載がないのであまり具体的なサポートができないのですが、一般論でいえば、設定が調整されていることによって発生する問題はペンタブドライバーなどの再インストール、設定周りのリセットをしていただくことをおすすめします。 -
RE: ペンタブ操作に関する質問ZBrushヘルプに投稿されました
ペンタブ操作でブラシサイズを変更やギズモ3Dの操作をする際に、前は一回のクリック後ドラッグでバーを動かせたのですが、今はダブルクリックしてからドラッグしないとバーを動かせたり、操作をしたりができません。
ペンタブ操作でスムースやブラシ操作をするとき、書き始めが遅延する(書き始めが入力されてない?マウス操作だと遅延しないです)以前は書き始めもしっかり入力されていたのですが、どうすれば直せるでしょうか?
これらは2つとも”一回目のタップを無視する”ようなペンタブの設定によるものだと考えられますが、Windows Inkなどが有効となっている場合にはインプットの遅延の原因となることが考えられます。上記理由から、使用しているペンタブの種類や、ペンタブレットのドライバによって異なるため、各社のサポート記事などをご参照ください。
-
RE: ポリペイントからテクスチャを綺麗に作成したいのですがZBrushヘルプに投稿されました
一番下のサブディビジョンレベルで、UVマスターの”クローンで作業を行う”を押すとサブディビジョンレベルがない状態のメッシュが別ツールで作成されるので、その状態でUVをアンラップします。
その後、UVコピーを押し、元のツールに戻り、UVペーストを押します。
これで一番下のサブディビジョンレベルでUV展開をしつつ、サブディビジョンレベルのあるメッシュにその展開したUVの結果が反映されます。その後、テクスチャマップ>ポリペイントから作成でその”ジレンマ”が解決できます。
-
RE: KeyShotBrigeが機能しなくなりました。ZBrushヘルプに投稿されました
@ERURA
Keyshot Bridgeに関連する不具合の場合にはZBrushのサポートへお問い合わせいただくことをおすすめします。
https://support.pixologic.com/こちらのページの"Start a conversation"より詳細をお送りください。
ですが書き込みを見る限り、根本的な原因はBridgeではなく、Keyshot11がアクティベートできないことが本来の問題ですよね?Keyshotはバージョンごとでのアップグレード購入が必要となっています。そのため、Keyshot10のシリアルナンバーではKeyshot11では使用できません。Keyshot11を購入しているにも関わらずアクティベートできない場合には、開発元のLuxionのサポートへお問い合わせが必要な内容となります。
2021年12月1日以降Keyshot10を購入している方には無料アップグレードの権利がありますので、サポートへお問合せください。
Keyshot10を今まで通り使用する場合には、先にKeyshot10を起動した状態で、BPRボタンを押すことで、再度ブリッジの設定がKeyshot10のほうを優先するようになり、次から送る際にはKeyshot10を利用するようになります。
-
RE: マテリアルの保存についてZBrushヘルプに投稿されました
マテリアル複製を押すとそのマテリアルの設定がコピーされるので、別の同じ系統のマテリアル(matcapではmatcap / StandardマテリアルではStandardマテリアル)を選択し、マテリアル貼り付けをクリックすることで設定をペーストできます。
これで同一設定のマテリアルが出来上がるので、こちらを調整し、保存することで使用可能となります。
-
RE: マテリアルの保存についてZBrushヘルプに投稿されました
2通りのやり方があります。
A.マテリアル複製後、設定を調整する方法
既存のマテリアルは変更されず、複製後のマテリアルは別マテリアルとして調整できます。
B.既存のマテリアルを調整後、保存後、アプリケーションを起動しなおし、保存したマテリアルを読み込む
-
RE: STLファイルのimportについてZBrushヘルプに投稿されました
ツールとして読込後、キャンバスにドラッグして配置、その後編集ボタン(またはTキー)を押すことで、3Dメッシュとして編集可能となります。
-
RE: トランスポーズラインのオレンジ円と赤円の比率の変更?ZBrushヘルプに投稿されました
@star0worshipper
トランスポーズラインの移動後のアンドゥや、赤円の比率調整は現状できないですね。
もし可能でしたらサポートチケットにて要望を出していただければ幸いです。検索ができない件承知しました。確認いたします。
-
RE: 複数のサブツールに同時にディバイドをかけるやり方ZBrushヘルプに投稿されました
マクロを組むことは可能ですが、サブツールごとにそれぞれのディバイドをできるのがサブディビジョンレベルのメリットの一つなので、ソフトウエア的にはあまり利点にはならない上に、まとめてディバイドすることであとで見返した際に不要な密度となっていたり、サブツール数によってはパフォーマンスが低下することが想定できます。
-
RE: 一部のメッシュがfbxでインポートできませんZBrushヘルプに投稿されました
何かエラーメッセージなどは表示されていますか?
特に表示されていない場合には、多くの場合、名前かぶりや、命名に問題がある場合、メッシュである場合や、OBJにはなく、FBXのみで書き出せる設定等に問題があるなどが想定できます。